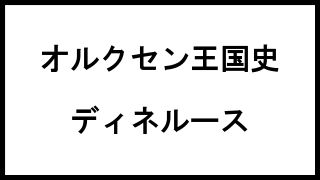原作小説「オルクセン王国史」ディネルース・アンダリエルの名言・台詞をまとめていきます。
オルクセン王国史 1巻
第一部 第一章
なぜ。本当になぜ。
オークとは、もっと凶悪な、非文明な生き物のはず。
それがどうしてこれほどの医療を。
人間族たちの言うところの、科学的なものを。
なぜ、私を助ける。
膨大な数ゆえに常に飢え、周囲の種族たちをも喰らう存在のはず。
あり合わせ? これが。
我らの郷土料理は、日常的にはこれほど豪華ではない。
ふつふつと気力までが満ちるとともに、思い出したくもないことも蘇ってきが。
──血の匂い。悲鳴。銃声。炎。殺戮。
──戻らねば。故郷へ。
白エルフどもを、ひとり残らず殺すために。
「(これから?) 戻る。戻るつもりだ」
「氏族の者たちを助け、他氏族とも手を取り合い、可能な限りの抵抗をする」
「代償に払う糧すらないゆえ、それさえ叶えていただけるなら」
「私は貴方に我が命を捧げよう」
「必ずここへ戻ってくる」
「そのあとでなら、私を食べてもらおうと、牝として扱ってもらおうと構わない」

「我らに救いの手を差し伸べてくださり、感謝致します。そうでなければ」
「我らダークエルフは滅んでいたでしょう」
「お約束通り、私ディネルース・アンダリエルの命は」
「ただいまこの瞬間から王ただひとりのものと思ってくださって結構です」
「我が王(マイン・ケーニヒ)」
第二章
どこかの国の実情を知りたければ、その国で発行されている新聞の三面記事に目を通すか、
大衆小説を読むか、市場へ行けなどと俗に言うが、
なるほど、納得の光景ではある。
──このお方は、信じられないほど優しい王なのだ。
しかも権力者にありがちな過剰な飾り気が、まるでない。
──この方の才はまるで異質。
何か、我らとはまるで違う、別の世界を見てきたかのような深慮遠謀がある。
彼の最大の欠点は、そんなところではなかった。
──周囲の臣下や側近たちがどれほど勧め、諌め、宥(なだ)めても、
妃や愛妾の類を持とうとしないのだ。
「世の万事、困難なほど成すまでには時間がかかる」
第三章
我らが狩猟を糧とすることはもう無いかもしれない。
だが、軍事行動という、もっと物騒で、無慈悲で、非情な「狩り」をやることになる。
このオルクセンという国は。国家が軍隊を動かしているのではない。
軍隊が国家を動かしているのだ。
「貴方は我らが降りるとは最初から露ほども思っていない」
「そしてそれに気づかぬ我らとも思ってもいまい。本当に馬鹿にしている」
もはや我らに白銀樹(ふるさと)はない。
悲しむべきかな、故国だった国こそが世でいちばん憎き相手だ。

第四章
いきなり飯の手配とは実にオーク族の軍隊らしかった。
悠長なようにも見えるが、食えるうちに食っておくのはいいことだ。
戦場での温食は何よりの贅沢品、士気を高め、継戦能力を維持する。
唖然としてしまう(食事)量だ。他種族の倍はある。
兵站が異常なまでに発達するはずだ。
──訓令戦術(アオフトラークス・タクティクツ)という。
上官の意図を部下たちは解し、戦闘の状況に合わせ、解決を図る。
誰も彼もが、大鷲そのものを銃口で追っている。
あれでは当たらない。
地上の獲物でもそうだが、空を飛ぶものなら尚のこと、
獲物が進む方向──未来位置を予測して撃たなければ。
このような極めて近代化された軍を打ち破る方法は、それでも幾つか存在した。
もっと大規模な火力や兵力をぶつけるか、回り込むか、だ。
第五章
「エルフィンドの軍隊は、相手の指揮官、将校を狙い撃ちにします」
第六章
心を持つ者同士の、距離、間隔、情緒というやつほど厄介なものはない。
何かをきっかけにそれまでよりずっと深まることもあれば、
下手に弄ると時間をかけて築きあげたものを一瞬で壊してしまうことがある。
「王。我が王。グスタフ。貴方もそう(転生者)なのではないか?」
「貴方は、どこか別の世界の、元人間ではないかな?」
「貴方がときおり語る、貴方が記憶や書籍のなかから探ったという専門用語の多くもそうだ」
「おそらく、まるで別の世界にあった用語だろう」
「貴方…これは私の勘違い、傲慢かもしれないが…」
「グスタフ、貴方。この私に興味があるのだろう?」
「貴方のまなざし、言葉。心遣い。ここしばらく接してみて、確信が持てるようになった」
「そして私の種族は、容姿としては極めて人間族に近い」
「最初は我が種族から何も差し出すものが無いゆえ、我が命も体も捧げると言ったが」
「いまでは本心からそうなってもいいと思っている」
「…ダークエルフは、人間ほどやわな存在ではない」
「たぶん…そう、たぶん大丈夫だろう。試してみなければ、わからないが」
最後まで読んで頂きありがとうございました。
アマゾンリンク
コミックシーモアリンク